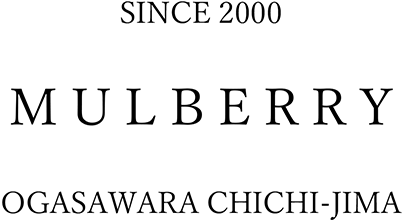夜明・湾岸道路一周での自生植物(3)ヒメツバキ

目次
はじめに
夜明・湾岸道路一周で見られる自生植物は
90種類ほどある。
一種類ずつ順に紹介していく。
(3)ヒメツバキ(ツバキ科・固有種)
ヒメツバキは
父島列島の山地ではごく普通に生えている。
ただし、高木性樹木なので、
乾性低木林のあたりでは少なめ。
山中では巨木クラスの大木になる樹木だが、
道路沿いではそこまで大きなものはない。
初夏のころからの花期には、
集落から山中までいたる所で落花が多く見られる。
小笠原の自生ツバキ科植物は本種のみ。
近年、
ムニンヒサカキはサカキ科となっている。
ヒメツバキの近縁種は
沖縄などで自生のイジュである。
この道路では、
夜明道路沿いでほとんどの場所で生えています。
また湾岸通り沿いでも見られる。
島一周 | 小笠原マルベリー (ogasawara-mulberry.net)
和名
本種はムニンヒメツバキともいわれる。
しかし、初めはヒメツバキとつけられた。
その後の経緯を経たうえで、
近年、また元のヒメツバキに戻している。
ヒメツバキは「姫椿」と書く。
幹はかなりの大木ににまでなる。
ツバキに比べれば、
花がこぶりでかわいいということなのであろう。
島名ロースードで、
ROSE WOOD がなまったもの。
バラの花(の香り)のような樹木という意味のようである。
花

1本の個体につける花の数はとても多い

花は村の花となっている。
小笠原村の花、木、鳥、魚の指定 (vill.ogasawara.tokyo.jp)
花期は5-6月頃からで、かなり多くの花をつける
個体数も多いせいか、花期も長め
冬場でもわずかですが、花が咲いているところがある

花は乳白色5弁、おしべ多数、めしべ1
5弁とはいっても、整った5弁ではなく、
1つの弁がお椀型で小さくなっている
他の4弁に比べ、痛んでくるのが早いように思う
花の咲き始めはおしべが鮮やかな橙色だが、
古くなった花だとおしべが黒みを帯びている
すぐ見分けがつく

花期には路上に落花も多く見られる
落花の多い時期は路面が滑るので、バイク・自転車は要注意
転ばないように気をつけて
果実

果実は朔菓
冬場に熟して5裂する

それぞれの裂片には
2つの薄い平べったい種が入っている

種はかなり薄いので、
風である程度飛ばされていくのもあるだと思う
葉

葉は互生ですが、枝先に集まる傾向にある
形は長楕円形で、先は尖り気味(尖らないのもあり)
縁には鋸歯はない
近縁種のイジュには普通、鋸歯がある

春先の新葉
初めは赤味を帯びている
幹・樹皮

ある程度大きくなると、樹皮に縦横のひび割れが目立つ
色は褐色だが、若い個体は薄い色のものもある

幹は枝分かれも多い
見るには
ヒメツバキは集落から山地まで
高木性の樹林ではたいがい見られる。
山地で普通に生えているので、
ほぼ全てのツアーで紹介できます。
前の記事へ
次の記事へ