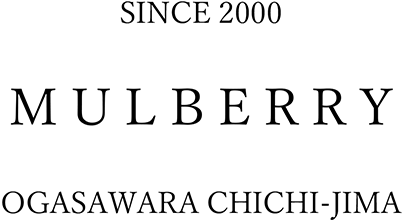夜明・湾岸道路一周での自生植物(90)ムニンシダ

目次
はじめに
夜明・湾岸道路一周で見られる自生植物は
90種類ほどある。
1種類ずつ、
特徴や見られる場所を紹介していく。
島一周 | 小笠原マルベリー (ogasawara-mulberry.net)
概要
シンプルな和名、
ムニンシダ(チャセンシダ科・広域分布種)。
小笠原(の)シダという意味ですが、
広域分布種なのです。
国内では小笠原だけの分布ですが、
海外は台湾や旧世界熱帯地地方などに広く分布します。
国内では小笠原でしか見られないから
和名にムニンがついたのはわかります。
でも、
なぜ特徴をあらわす言葉をつけなかったのでしょうか。
初出を知りたいものです。
小笠原での分布は父島、兄島、母島などです。
父島では山道沿いでも見ますが、
それほど多くはないように感じています。
普通、沢沿い・湿っぽい場所の岩場に生えています。
このルート沿いでは、
中央山付近の崖地でわずかに生えている。
ただし、分かりにくい。
本種の葉は
やや変形したひし形で特徴的です。
和名
ムニンシダは「無人羊歯」と書きます。
つまりは
小笠原のシダということなのです。
ムニンは、
かつて無人島(むにんじま)と言われていた名残で、
小笠原のこと。
樹木にも
ムニンノキというのがあります。
生えている様子

夜明道路沿い、
中央山付近の崖地に生える個体

岩場の上に生えている個体
すぐ下は沢のある場所
.
葉身は単羽状複生

葉の形は
ひし形を細くし、非対称の形にしたようなイメージ
羽片の長い側の縁は鋸歯となっている
先端の頂羽辺は、それより下の側羽片より大きめ

胞子嚢群は中肋から線形で複数本並びます
見るには?
父島では、
ムニンシダの生息地は限られています。
そのため、
ツアーで紹介することもあまりありません。
しいて言えば、
千尋岩コースでは道沿いにあるので、紹介できます。
興味のある方はお知らせください。
参考
前の記事へ
次の記事へ