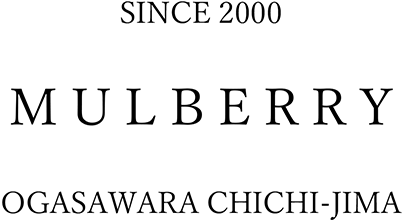夜明・湾岸道路一周での自生植物(8)クワノハエノキ
目次
はじめに
夜明・湾岸道路一周で見られる自生植物は
90種類ほどあります。
奥村・旭橋から時計回りで、
主には見られた順に紹介していきます。
(8)クワノハエノキ(アサ科・広域分布種)
かつてはムニンエノキ・固有種とされていました。
現在は小笠原のものも、
クワノハエノキ(広域分布種)という見解となっています。
高木性の樹木ですが、
父島では目立つほど大きいのはめったにありません。
自生種では数少ない落葉樹です。
小笠原では
アサ科のエノキの仲間は2種のみです。
ウラジロエノキとクワノハエノキ
(どちらも広域分布種)です。
このルート沿いでは
夜明け道路沿いでぽつぽつと見られます。
葉

これが葉です。
クワの葉に似ているからクワノハエノキなのです。

オガサワラタマムシは
本種を食草にしたり、卵を産み付けたりしています。
夏場は本種を集中的にチェックすれば、
たいがい見つかります。

10月ごろ落葉
その後すぐ新葉を展開します。
新葉の展開とともに、花期を迎えます。

新葉が広がる様子
花
花期は11-12月頃ですが、
花を見ることはめったにありません。
あまりつけないのか?小さいので気づいていないのか?
さてどちらでしょうか?
花は雌雄同株ですが、
花は両生花・雄花が分かれています。
花被片4は共通です。

花被片4ですが、雄花はおしべ4が目立ちます。
おしべと花被片が重なったようになっています。

花被片4ですが、
両生花はめしべの柱頭2裂が目立ちます。
奥におしべ4もあります。
両生花と雄花があるから、
実質、両生花が雌花の役割ですね。
果実

果実は径が1.5㎝ほどの球形
見るには?
道路沿いや林縁など比較的明るい所で見られます。
あまり目立たない樹木で、
印象に残らないかもしれません。
各種ツアーでご紹介できます。
前の記事へ
次の記事へ